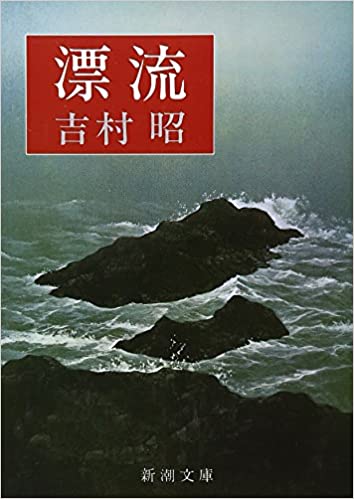「漂流」(吉村昭・新潮社・昭和55年11月25日発行)は令和3年10月25日64を数えている。これだけの名著を評するなんていうことは僭越も甚だしいが、私なりの視点から思うままに書いてみようと思う。
舞台は江戸・天明年間(1700年代)である。シケに遭った土佐の水主である長平は黒潮に流され仲間と共に絶海の孤島へ漂着するのだが、まず、シケの中に翻弄される舟、軋み音を立てて傷んでいく舟、今にも木端微塵になり海へ投げ出されそうな様子はページを捲る手を早めていく。この臨場感は恐怖である。
そして、島へ漂着してからの壮絶な暮らし、水、食料の確保から始まり、弱っていく仲間との死別の描写はリアリティーがあり、いつしか読者は長平たち仲間の一人へと誘い始めるのだ。また、思いもかけない新たな仲間の加入。忘れてはならならないのが、無数にいるとも思える大鳥(アホウドリ)の存在である。彼らの主食になるだけでなく、卵の殻は水を貯めるための重要な容器にもなり、また、彼ら以外の唯一とも思える“命”の存在は大きな慰めであると同時に、渡り鳥であるがための別れ、再会を繰り返す。繰り返すということは、またこの一年もこの島から脱出できずに、この島で死を迎えることが近づいているとも言えるのだ。この間、長平は自ら死を選ぼうともする。全く普通の若者であったのであるから当然と言えば当然だ。しかし、全てを神仏に委ね、念仏を唱えることで心を泰平に保つ様は、神々しくさえ移る。一人の若者の成長期でもあるのだ。壮絶すぎるが。そして、時は流れ12年の後、長平はこの島から脱出することに成功するのだ。この過程は、果てしなく長いのだが、それをやり遂げたことには感動を覚える。詳細は一読の価値があるはずである。
これだけ壮絶なストーリ―をドキュメンタリー小説として描くのは、筆者の並々ならぬ取材の賜物であろう。しかし、取材だけではなく、物語として紡ぐための想像力、描写力、構成力が伺える。数多くの著作を残している筆者について更に興味が湧く1冊と言えるだろう。
また、この1冊を読んで、以前読んだ以下の本が思い出された。合わせて一読してみてはいかがだろうか。